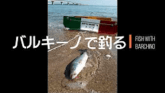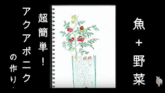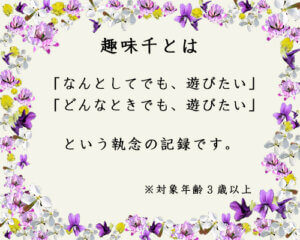前回の記事はこちら↓
←1万円、1日で!石窯の作り方~②土台のブロックと平板を買う~
この記事のシリーズ第1回目はこちら↓
←1万円以内、1日で!石窯の作り方~①耐火レンガと陶器鉢を買う~

目次
石窯に適した土は?
粘土だけで作った窯は「石窯」ではなく「土窯」とか「コブオーブン」と呼ばれます。陶器の鉢やレンガを、土で覆ってしまう窯の場合は、土窯やコブオーブンではなく、石窯の分類になります。
石窯を作る上で必要な土は、ある程度の粘りがあればどんな土でも構いません。屋根瓦を葺くのに必要な屋根土や、田んぼの深い層にある粘土はとても優れていますが、最も手に入れやすいのは赤土でしょう。逆に不向きなのは真砂土などのさらさらして固まらないもの。陶芸ができるような完全な粘土でなくても、水をかけておにぎりを作るように固めて放置し、乾燥してもバラバラにならなければ大抵の土は石窯に使えます。
赤土は様々に利用されてきた!
赤土は関東ローム層という火山灰です。きめが細かく、水を含むと粘りけが出ます。ある程度湿ったものは強い圧力を加えると、石のように硬くなります。これは「鋼土」と呼ばれ、ため池の防水工事などによく使われてきました。
昔の日本のどこの家庭にもあった「かまど」や「くど」も、この赤土で作られたものが多くありました。赤土がひび割れないよう、にがりを混ぜて練り、各家庭でそれぞれかまどを自作していました。
石窯に使う赤土を入手しよう!

赤土は採石業者や建材店などに頼めば売ってくれます。林道の工事現場などで大量に出た場合、交渉すれば「タダでいくらでも持っていって構わない」と許可が出ることがあります。通信販売などで購入すること も可能ですが、なにしろ土なので重く、送料がかさんでしまいます。農協などが近くにあれば、籾まき用の赤土が売っていることもあります。
なかなか手に入らない場合は、ホームセンターの園芸コーナーに売っている「赤玉土」を使いましょう。赤玉土は赤土をふるいにかけて大粒、中粒、小粒に分けたものなので、潰して粉にすると赤土に戻ります。焼成したものでないほうが、潰しやすいようです。
赤土に粘りを加える
赤土や赤玉土が手に入ったら、よく練って粘りを付けましょう。赤玉土はコンクリートなどの固い地面の上で踏み、粉々にしましょう。赤土を練るのは「トロ舟」や「プラ舟」と呼ばれる、セメントを練るための容器に入れて作業をすると、楽です。水を少しずつ加え、次第に粘りを出していきます。足で踏んだり、ショベルで混ぜたりし、最終的には味噌と同じくらいの粘りになるように調節します。

納豆菌の登場
本格的に赤土に粘りを付けたいなら、ここで稲わらの登場です。稲わらは納豆を包んでいることからわかるように、稲わら自体に多くの納豆菌が付着しています。稲わらを5センチほどの長さに裁断し、赤土に混ぜ込んで放置します。そうしておくことによって納豆菌が繁殖し、粘土に粘りが出てきます。稲わら自体も粘土のひび割れをある程度防ぐ役目もあります。
稲わらの切断は以外と面倒です。「ワラ切り」という専用の刃物を使うのが便利ですが、現在は農家でも持っているところは多くありません。ワラ切りが無い場合は、枝切りばさみなどを使うと安全です。
石窯に使う赤土に草を混ぜ込む

練り上がった赤土に、草を混ぜ込みましょう。できれば乾燥させた枯れ草が良いでしょう。エノコログサやチガヤなど、30センチ前後の長さの長い草が適しています。もし草がなければ、新聞紙や木綿の古い布などを裂いて混ぜても良いです。
混ぜ込む草の量はかなり多くなります。草を含む粘土を団子にしても、しっかりと固まったままの粘りが維持できるのであれば、限界まで混ぜ込んでも構いません。
草は石窯の保温力を作る
赤土に混ぜ込んだ草やワラは、赤土の中に多くの空間を作ります。この空間が、発泡スチロールのように多くの空気を抱き込むようになります。この層が石窯の熱を逃がさず、いつまでも蓄熱 してくれる要となります。保温力をより高めるために、もみ殻などを混ぜ込んでもOK。ボラと呼ばれる軽石なども、混ぜ込むと保温力を高めてくれます。
砂を混ぜると石窯のひび割れ防止に
石窯の粘土層は、強い火力が加わったり乾燥したりすると収縮し、どうしてもひび割れてしまいます。ある程度のひび割れは仕方なく、のちに補修を繰り返すことになるのですが、砂を一定量混ぜると、乾燥の際のひび割れをある程度防止することができます。加える砂の量は粘土の質によって調整する必要があり、一概には言えませんが、あまり多く入れると粘土の粘りが減少し、後の作業が難しくなります。次の石窯の作り方は「土台の工事」です。